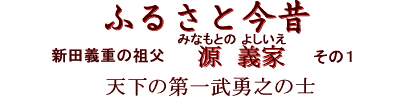
 八幡宮(新井町) 太田・新田地方の中世を開き、新田荘開発領主新田義重の祖父は、清和源氏の主流で、平安時代後期の武将として知られる源義家である。 義家は長暦3年(1039)に父源頼義・母平直方の娘との間に長男として生まれ、幼名は源太という。石清水八幡宮で元服(成人)したので、八幡太郎源義家と称される。清和源氏の内、義家系は河内国(大阪)に本拠をもつ中流貴族で、摂関政治を行っていた藤原氏に仕える武官・武者として政権を支え、郎等・郎従などの従者をひきいて活動していた。 このような家で生まれた義家は武者として成長し、「猛将」「弓道の達者」「天下第一武勇之士」「武者の長者」などと杯され、「武威天下に満つ、誠に是大将軍に足る者也」と評されている。 義家は左馬尉(さまのじょう)・左衛門尉・左近将監(さこんしょうげん)・左馬権頭(ごんのかみ)・兵部大輔・検非違使(けびいし)などを経て、下野・相模・武蔵・河内・伊予・信濃・出羽などの守を歴任し、正四位下に叙せられ、永保3年には陸奥守兼鎮守府軍に任じられている(系図『尊卑分脉』)。 「当代随一の武者」義家は、次号に述べる「前9年の役」「後3年の役」で大活躍し、武名を高めた。 |
前9年の役のころ、公家の大江匡房(まさふさ)に「未だ兵法を知らず」と評されたが、それに反発するどころかむしろ匡房を師と仰ぎ、兵法を学んだと伝えられるように、義家は謙虚、真面目の一面をもっていたようである。 後3年の役では、この戦乱は清原氏一族の内紛であり、私闘であるとして、朝廷は追討の宮符を出さなかった。義家はやむなく私財を投じて共に戦った将士の労に報いたという(安田元久『源義家』)。 武門の長者であり、人望の厚かった義家はやがて関東の在地領主と関係を深め、源氏の勢力が浸透するようになった。鎌倉時代に本市はじめ各地に「八幡神社」が歓請されることで、義家の影響力の大きさが分かる。 嘉承元年(1106)7月、病気によって68歳をもって死去した。墓は大阪府羽曳野市の史跡通法寺跡にある。  源義家(『後三年合戦絵巻』より) |